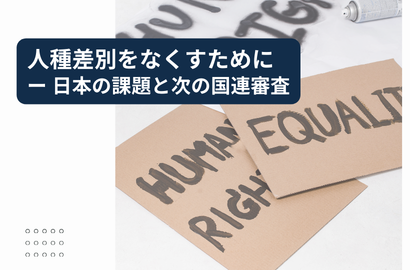ニュース
第6次男女共同参画基本計画案へのパブコメ提出
男女共同参画社会基本法(1999年)のもと政府は男女共同参画基本計画を策定し、これまで5年毎に基本計画の見直しをしてきました。今年2025年は第5次基本計画の最終年にあたります。そのため、内閣府男女共同参画局を通して、政府は「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」を発表し、8月26日から9月15日までの3週間、ウェブサイトなどでコメントを公募しました。
当初より、基本計画にマイノリティ女性に関する政策や措置の言及がないことに対して、IMADRとマイノリティ女性フォーラムは政府に申し入れを行ってきました。その結果、2010年の第3次基本計画より、ようやく「複合的に困難な状況に置かれている」として、日本で生活する外国人、アイヌの人々、同和問題というくくりで女性たちの存在を計画に含めるようになりました。しかし、「困難な状況」という言葉が示すように、その対応は、あくまでも困った人を支援するという立場に留まっており、民族、出身、障害の有無、性的指向や自認、ジェンダーなど、異なるアイデンティが交差することにより生じている複合差別の認識に立った対応や措置とは言えません。
IMADRは第6次の基本的な考え方(素案)へのコメントとして、主に次の点について意見を提出しました。要約にて報告いたします。
<< IMADRのパブコメのポイント>>
*性的マイノリティであること、障害があること、外国人やルーツが外国であること、アイヌの人々であること、被差別部落出身であることなどの属性に基づく差別と、女性に対する固定観念や偏見による差別が交差し、複合的な結果をもたらしている。そのため、「複合的な困難」ではなく「複合差別」として示すべきである。
*外国人やルーツが外国であることという表示は「旧植民地出身者とその子孫である在日コリアンを含む外国人やルーツが外国にあること」にすべきである。同じく、「部落差別(同和問題)に関すること」という無人化の表示ではなく、「被差別部落出身者」など、そこに人びとが存在していることを示す言葉にすべきである。
*被害女性の側面より、法務局の人権調査救済相談体制は特に次の点において充実させるべきである。
i) 相談窓口へのアクセシビリティ
ii) 調査案件については、その進捗状況に関する情報を適切に相談者に知らせる
iii) 相談員の専門性(国際人権法を含む人権に関する法や制度の十分な知識)
iv) 相談員の専門性(国内の様々な人権課題の知識と理解、被害者への対応におけるスキル、他)
v) 調査・相談終了後のフォローアップ
*法務局による人権調査救済相談体制ではなく、繰り返し国連から勧告されてきた「パリ原則に沿った政府から独立した国内人権機関」の設置を検討すべきである。
*女性差別撤廃条約を国内で実効的に実施するために「女性差別の定義」と「個人通報制度の採用」が必須である。