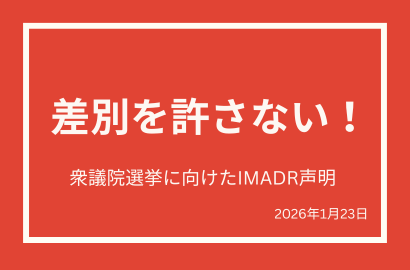イベント&キャンペーン
Intersectional Feminism #3 親川裕子さんにインタビュー
新シリーズ、インターセクショナル・フェミニズム。第3弾としてお話を伺ったのは、沖縄県中南部に位置する宜野湾市で生まれ育った親川裕子さん。
沖縄県には米軍基地が多数存在し、日本にある米軍専用基地の約70% が沖縄県に集中しています1。親川さんの地元である宜野湾市には普天間基地があります。普天間基地は沖縄戦の最中に日本本土への攻撃拠点としてつくられたのが始まりだと言われています2。

学生時代で鮮明に覚えてることはなんですか?
「私は普天間基地の近くで育ったので、大きな騒音には慣れていました。米軍のヘリコプターは学校の授業に関係なく飛ぶため、授業が中断されることは日常茶飯事でした。例えば、国語の授業で教科書の音読をするとき、他の生徒に声が聞こえるように、ヘリコプターが通過するのを待つように言われました。実際、基地周辺の学校に通う子どもたちは、授業が大音響でよく中断され、小、中、高の12年間で約1年分の授業を受けられなくなるそうです。沖縄の子どもたちの学力にも影響していると思います。大学進学で沖縄北部の名護市に引っ越したとき、軍用ヘリがないだけでこんなに静かなのか、と驚きました。大学生活は、沖縄県内での異文化コミュニケーションでした。例えば、小学校から高校まで、通っていたそれぞれの学校にはクーラーがあり、窓は二重ガラスでした。また、小学生の時にはプールができました。しかし、沖縄の他の地域から来た人たちは、そのような設備がなく、うらやましがっていました。後になって、これらの設備は基地周辺整備のための予算から捻出されたものだと知りました。さらに、那覇市や沖縄島南部の人たちは、軍の音がどれほど大きいか知りません。そのため、私のような体験をしていないことにとても驚きました。大きな音など、日常生活の中にあるものだったので、それがおかしい、差別だと気づくのには時間がかかりました。」
米軍用ヘリコプターの音はこのインタビュー中にも聞こえました。二重窓でも、防音できない音量、軍用機には消音機能がなく、音が大きくでる作りになっていると親川さんは教えてくれました。
何がきっかけで、アクティビズムに関わるようになるんですか?
「1995年、私が大学2年生の時に3人の米軍兵士による少女レイプ事件が起きました。当時、政治に興味がなかった私は、おかしいと思いつつもこの問題を友だちと議論することはありませんでした。その翌月に、沖縄で1972年以来最大の抗議集会であった大きな県民大会が開かれ、約8万5千人が集まりました。そのニュースを読んで、参加すればよかったと後悔しました。それまでは、米軍基地があるから被害があるのは仕方ないと思っていたんです。しかし、このニュースを見て、怒ってもいいんだと気づかされました。同時に、無意識のうちに諦めていたことも痛感しました。今思えば、この事件はいろんな意味で私の転換点となりました。」
それからずっと関わり続けているんですか?
「いや、普天間基地の名護市への移設を市長が受け入れた時点で嫌気がさしてそれ以上関わるの一度、やめました。1997年に行われた名護市住民投票の結果、半数以上が基地移設を拒否しました。この姿勢は前年1996年に行われた県民投票にもあらわれていて、約9割が基地縮小に賛成しました。私たち沖縄の人々はいつも経済か基地かの二者択一を迫られているのですが、沖縄の人々の意志をこれらの投票で示しました。しかし、名護市の住民投票の数日後に当時の市長が基地移設を受け入れ、自らの辞職を宣言しました。つまり、市民の意見よりも経済活性化策を優先し、私たちの声は完全に無視されました。そんな政治に嫌気がさして大学卒業後に地元に帰り営業として働いていました。」
そこからもう1度関わろうと思ったきっかけは何だったんですか?
「社会人になって2年くらいたった頃、友人から国際人権に関するワークショップに誘われたのがきっかけです。そのワークショップに参加した時に、先住民族の権利について講演を聞きました。そこで初めて、軍事基地を含む沖縄の問題は国際人権法の観点から国連で訴えることができる可能性があり、問題自体が沖縄の人びとに対する人権侵害であることを知りました。それまでは、被害というよりも経済活性化策の問題として捉えられることがほとんどでした。しかし、このような新たな知見に出会い、沖縄の歴史を振り返ると、確かに「人権問題」として捉え直す必要があると強く感じました。また国内法では限界があるため、国際的な人権の枠組みを使うことにしました。その後の縁で2000年に行われた国連の先住民作業部会に参加することになりました。そこで、日本にいると特殊に感じる沖縄が抱えさせられている問題は先住民族の普遍的な問題であることを知りました。」
今まで1番印象に残ってる活動はなんですか?
「2009年に行われた女性差別撤廃委員会 (CEDAW) による日本政府報告書の審査が行われたときのことは印象に残っています。中でも、アフガニスタンの Zohra Rasekh 委員にロビーイングしたことは忘れられません。私は、沖縄県における低出生体重児の割合が、全国平均の2倍であるということに触れながら、爆音が妊娠中の人びとに及ぼす影響について話しました。特に、米軍基地のある地域では、沖縄県内でも低出生体重児の割合が最も高かったのです。その原因は様々でしょうが、政府はきちんと因果関係を調査すべきだと伝えました。するとセッション中に、Rasekh 委員が日本政府に対し騒音による健康被害とそれに対する政府や自治体の対応について、質問してくれました。そこで、条約審査の面白さとともに国際社会で発言することの大切さを実感しました。」
国際人権法だけでなく、ジェンダーやインターセクショナリティの視点からも沖縄の問題を分析している親川さん。
ジェンダーの問題に関わるようになったきっかけはなんだったんですか?
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の制定にむけてドメスティック・バイオレンス(DV) がメディアでよく取り上げられたことがきっかけで、DVってなんだろう、ジェンダー問題ってなんだろうと関心を持つようになりました。そんな時、嘉手納基地を抱える北谷町で男女共同参画行政(当時は「女性行政」といっていましたが)をサポートする非常勤の職に誘われました。そこでの経験もジェンダー問題により興味を持つきっかけになったと思います。」
複合差別の問題にはどのように出会ったのですか?
「北谷町の男女共同参画行政で働いていた時に、再び米軍によるレイプ事件が、地元北谷町の若者が多く集まるようになった場所で起きました。『またか』と思いました。その時、誰よりも先に強い抗議行動を始めたのは地元の女性たちでした。それを見て、男女共同参画行政の推進だけでは沖縄の問題、特に米軍による性暴力の問題をカバーしきれないと感じました。刑法や日米地位協定3の関係で警察は被害者が申告しないと動かないし、米軍の許可がないと軍人の被疑者を逮捕することもできません。つまり、沖縄の女性たちは国内法と日米安保と、二重、三重にも不利益を被っていると強く感じました。それらに地元の女性たちが強く激怒し、率先して声をあげている姿に勇気づけられました。そんな時、東京で開催された複合差別研究会に参加していた友人から初めて『複合差別』という言葉を聞いたとき、事件と重なり、これは沖縄の女性にとって重要なキーワードになると確信しました。一言でマイノリティ女性といっても、共通点もあれば相違点もあります。そのため、他のマイノリティ女性たちとの交流をとおして、新たな発見や気づきがありました。」
現在、博士課程にも在籍している親川さん。
現在はどのような研究をしているんですか?
「現在は、戦後、1950年代、米軍占領下の沖縄で創設された「国際福祉相談所」と国際福祉について研究しています。例えば、1985年に改正されるまで旧国籍法では、母親が子どもに国籍を継承することは認められていませんでした。そのため、父親がアメリカ国籍であると生れてくる子どもは日本国籍を取得することはできませんでした。また、米兵と交際したり結婚した女性は、米国が強国と見なされていたため、否定的な偏見に晒されました。米兵の妻たちは米軍基地内の雑貨や食品など豊かな資源を得たり、利用したりすることができたため、嫉妬の対象ともなっていたようです。このような態度は、沖縄におけるジェンダー的問題の他者化、周縁化を示しており、「複合差別」、「インターセクショナリティ」の観点としても捉えられる問題だと思います。」
米軍人と結婚した女性とかに対するステレオタイプは今もあると感じますか?
「米軍人、軍属と結婚したり、子どもを持ったりする女性たちに対するステレオタイプ化された偏見というのは、今もまだあると思います。それら偏見の顕著な例が相談機関の不備だと思います。米軍人、軍属であるパートナーとの離婚やDV、養育費といったプライバシーの問題に対する相談機能の受け皿が沖縄を含めてですが、日本国内では不十分です。それは「彼女たちの問題」は「私たちとは違う」と一線を画し、問題を他者化、周縁化している証左のように感じます。確かに、米軍は日米地位協定上保護される立場で、日本国内でも特殊な存在であり、結婚や離婚といったプライバシーにかかる問題に対する解決方法も非常に困難です。だからといってジェンダー問題に取り組む人々が、その状況を偏見に基づき他者化、周縁化することを正当化することはできない。私自身も複合差別、インターセクショナリティ研究をするにあたって自戒の念をもってこれらの偏見に向き合わなければと考えています。」
親川さんは長い間、研究者として市民社会組織の一員として(特に沖縄に関する)社会問題に関わり続けています。
活動を始めた時と現在で何か変化を感じますか?
「そうですね。国際人権という点では、沖縄県知事が人権理事会(HRC)の場で声明を読み上げました4。沖縄の中でも国際人権の枠組みを使うことが注目されてきている、こうした変化を強く感じます。それと同時に、ジェンダーに関していうと、女性が非常にエンパワーメントされてきていると感じます。私が社会運動を始めた頃はまだジェンダー問題に取り組む人は”意識高い系”と思われていました。でも、若い世代が関わるにつれ上の世代の人たちもだんだんと変化してきていると思います。とりわけ沖縄においては、それらの背景には、今まで継続的に活動してきた女性たちの力強さを痛感しています。特に「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会5」を組織してきた女性たちが沖縄の性暴力やジェンダーの問題への解決、解消策を牽引してきました。彼女たちの努力のおかげで、 「被害者の落ち度」論に終始するレイプ神話は覆され「あなたは悪くない。悪いのは加害者である。」という認識が拡まってきました。
これらの様々な女性たちの活動の延長線上に2017年の刑法改正があり、今年2024年4月には「女性支援新法」(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)6 の施行があったことを踏まえると、声をあげることの重要性を痛感します。」
沖縄に住んだことがない人や行ったことがない人はどのように沖縄の問題に関わることができると思いますか?
「いろんなやり方があると思いますが、関心を持つことが一番だと思います。また、最終的に国としての意思決定をするのは国会議員で構成される政府なので、自分の地元の地域をよくしていくことが沖縄を支えることになるのではないかとも思います。簡単なようで難しい話ですけど、自分たちの住まいや地域、地方議会や首長選挙など足元の政治から変えていくことによって沖縄の問題にも変化をもたらすことができるのではないかと思います。なので、皆さんがお住いの地域が抱える課題や問題を無視しないで関心を寄せるということが大切であると強く思います。」
1 詳しくは沖縄県ホームページをご覧ください:https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/kodomo/1002657/1002668.html
2 詳しくは宜野湾市ホームページをご覧ください:https://www.city.ginowan.lg.jp/shisei/kichi/4/4277.html.
3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 (日米地位協定): https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
4 2015年に翁長知事、2023年に玉城デニー知事が沖縄の「自決権」に関してHRCで声明を読みました。
5 詳しい活動は団体ホームページをご覧ください:https://space-yui.com/